100人いれば100通りの『エサバ』(毎日野菜が採れる畑)になる『自給農法』。
そんな常識外れの農法に関してまとめています。
自然農法や自給自足に興味がある人にとっては、
ひじょーに役立つ記事になっとります。
今回はその②。
読んでいない方はその①からどうぞ。
さて、自給農法ではなぜ無農薬・無肥料でもしっかりと育つのか?
その答えは下の4つ。
② 『次世代土壌』を活かす
③ 分け合うことで増やす
④ 土掛け3回肥料いらず
それでは詳しく解説していきましょう。
『無肥料』『無農薬』でもしっかりと育つ!?
植物が育つために必要なもの。
それは、
『光』『水』『空気』『土壌の栄養素(窒素・カリ・リン)』
そして植物自身の『光合成』ですよね。
だから現代の農業の考え方では、
・肥料で土に栄養素を補って
・病気が出ないように農薬まいて
・栄養を雑草に取られないように排除
するんですね。
そして収穫が済んだ畑は、
土が硬くなっているからまた耕して、
栄養がなくなっているからまた肥料を施して、
雑草や病気の予防にまた農薬まいて…
とまあ大変です。エンドレスにお金も手間もかかります。
それにしても…
農家の人はこんなに苦労して野菜を作るのに、
その割に野菜って安すぎますよね。
では『自給農法』は「植物が育つワケ」をどう考えているのか?
なぜ『無肥料』『無農薬』でもしっかりと育つのか?
その答えは
「なぜ自然の中では野草や木々が勝手に
(人間が手を加えなくても)健全に育っていくのか?」
を考えるところからはじまります。
①大地の再生力を活かす
『自然界はみんな共同で最後は森を作る』
講師のジャンさんに教わった印象的な言葉です。
ポイントは『みんな』。
人間が何も手を加えない土地は、
長い年月をかけて必ず最後には森になる…
植物だけにフォーカスした場合、
その移り変わりを『植生遷移』と言うそうです。
これは何となく知っていました。
しかしこの植生遷移は、実は植物だけの力では起きないのですね。
つまり『みんな』で森を作るというのは、
植物だけでなく、
菌も、虫も、鳥も、動物も、植物も、
すべての生き物のすべての営みが森を作る方向に働いている
ということ。
それは例えば…
鳥が木の実を食べて飛んだ先で種が入ったフンを落とす
イノシシが穴を掘ってそこに窪地が好きな植物が繁茂する
白アリが弱った木に巣を作ったことで木が枯れ、
菌のたくさん住む腐葉土となり、次の木をはぐくむ
このように『すべての生き物のすべての営み』は、大きく見れば森を作る方向に働くらしいです。
森を作る力=大地の再生力
自給農法は、この『大地の再生力』を抑え込むのではなく、
逆手にとってうまく活用する農法。
自然の持つ森に向かう力を手伝ったり助けることで、
病気にならず、肥料もいらない健全な作物が育つ方法。
そのために『感性』を働かせてその力(大地の再生力)を見抜き、
共同作業するようなイメージが必要になります。
今の農業は、大地の再生力を抑える方向にものすごく労力を使っている。
だから非効率なのです。
②『次世代土壌』を活かす
「次世代」とかいうと、
最新の土壌改良システムのようなイメージが湧くかもしれません。
しかしもちろんそうではく、
土壌は「もうできている」(※前回記事参照)と考えるから『次世代』なのです。
どういうことかというと、
植物はみな「次の世代のために土壌を作っている」ということであり、
具体的には根っこがつかんでいる土が「次世代土壌」となります。
自然の植物(野草や雑草)は、
自分の子供や子孫(次世代)が育つために最適な環境を
自分の根っこのまわりに作っている
ということです。
つまり野菜だろうと雑草だろうと、
何か植物が生えていれば、
そこには必ず次世代土壌が存在することになりますね。
これはなぜ自然界では『連作障害』が起こらないのか?
(雑草は毎年同じ場所に生える)
という問いを考えてみても納得できます。
土壌が持つこの本来の力を使えば連作障害も起こらない。
というよりも逆にどんどん連作に適していくということ。
この話を聞いたときには、
気持ちいいぐらい常識が崩壊し、
自然の摂理に沿った理論に心底納得しました。
よく言われる「土ができていない」のではなく、
「すべてここにある」と考えることから自給農法がはじまります。
植物が育つために一番いい土壌は、
雑草などがすでに作ってくれている。
「土はもうできている」んです。
ただ、ここでふと疑問が。
「理論は納得した。
でもさ…オレも雑草は排除しないでやってきたのに、
あまり育たなかったよ…なんで?」
その答えは講師のジャンさん語録からいただきます。
「野菜って、外人なんですよ(原産地はほとんど外国)。だから地元の人(雑草)がたくさんいるところに種をまいたり苗を植えると遠慮するんです」
「だからそこを手伝ってある程度勢いのある状態(根っこがしっかりとした状態)にしてあげられれば、今度は周りの地元の人が遠慮しはじめます(しっかりと育ちだす)」
「苗を作るはじめの1ヵ月で、しっかり収穫できるかどうかの7割が決まります」
「そういう意味ではホームセンターの苗はほぼ全滅です。ちゃんとした苗でないと、その後挽回するのはかなり難しいです」
なんだか…
全部人間と同じですね。
当たり前のことだけど、
なかなか気づけない視点です。
自然農法でよく言われる
『雑草を敵にしない』
『自然は耕さない(不耕起)』
などの素敵な言葉をうわべだけで実践してもダメってことがハッキリしました。
方法論ではなく、もっと当たり前の『感性』で向き合わないといけなかったんですね…
反省。
Q:具体的に次世代土壌をどう活かすの?
A:・根土を集めるために、雑草の根までの表層を削った土でウネを作る
・根土の中に種まきをする。根土のポットで苗づくりをする
詳細はまた違う記事で。
③分け合うことで増やす
ピラミッドで考えているのは人間だけ
…分け合ったら減らないにしても増えはしないのでは?
たしかに普通そう思います。
ここでもジャンさん語録をどうぞ。
「自然界はいつもバブル(終わらない)。倍々ゲームで増える」
「生き物はそれぞれの役割をまっとうしているだけ。どの行為も実は分け合っている」
「多様性があればあるほど豊かな場所になり、共存共栄できる」
例えば、お米(イネ)は「一粒万倍」と言われます。
実際には慣行栽培(一般的なコメの栽培方法)で多くて2,000粒程度(参考:クボタのタネ)。
それでも2,000倍ってすごいです。
たしか仮想通貨バブルでも1,000倍ぐらいだったのにそれ以上。
…しかも終わりがない!
そんなふうに倍々ゲームな自然界は、
全ての動物が分け合っているからこそ成り立つということ。
例えば…
ある虫を『害虫』として排除した場合
① その虫が食べていた草が増えすぎる
② 他の草が育ちにくくなる
③ 他の草を餌とする虫がいなくなる
④ その虫が好きだった鳥がこなくなる
⑤ その鳥のフンが好きな微生物がいなくなる
⑥ その微生物が好きだった病原菌が発生しやすくなる
⑦ 病原菌によって、さらに偏った植物しか育たなくなる
⑧ 繰り返しながら負のスパイラルへ…
とまあこんな感じでしょうか。
だから本当は、
雑草や虫がたくさんいる多くの生物にとっての
いい『エサバ』であればあるほど、
人間にとってもいい『エサバ』になるはずなのです。
『害虫』という言葉も、
人間サイドが勝手に思ってるだけ。
ほかの自然界からすればいい迷惑です。
そして、人間サイドの視点のみでその虫を駆除すれば、
回りまわって最後は人間に悪影響を及ぼします。
④土掛け3回肥えいらず
この言葉、わたしは初めて聞きました。
昔から日本の農家に伝わる言葉(格言?)だそうです。
講師のジャンさんが、
「他の内容は忘れても、これだけは絶対に覚えて帰ってほしい!」
と言ったほど重要なテクニックです。
具体的には、
収穫までに3回、ウネの側面の表面を雑草ごと削って、草と土をフワッと混ぜて(チャーハン状態と呼ぶそう)作物の根本にかける
これで除草と肥料やりが同時に完了するとても効率的・合理的な方法とのこと。
ちなみにジャンさんは
「5回とか7回とかいろいろ試したけど、結局3回以上は変わらないので、やっぱり3回が一番いい」
と言ってました。
ジャンさん、実践の人です。
これに関しては詳細な理論の説明はありませんでした。
ともかく古来からのテクニックとのこと。
自給農法が無肥料・無農薬で育つワケまとめ
①大地の再生力を活かす
②『次世代土壌』を活かす
③分け合うことで増やす
④土掛け3回肥料いらず
『思想的・感覚的』な内容と『科学的・実践的』な内容のバランスがいいですね。
個人的に今まで独学した自然農法は、
思想や思い(罪悪感や正義感)が色濃くて、
実際的な部分は弱いと感じていました。
それらに比べると
「これなら本当にいい野菜ができそう」
と素直に納得できるものでしたね。
それでは今回はここまで。
座学のまとめは次回も続きます。







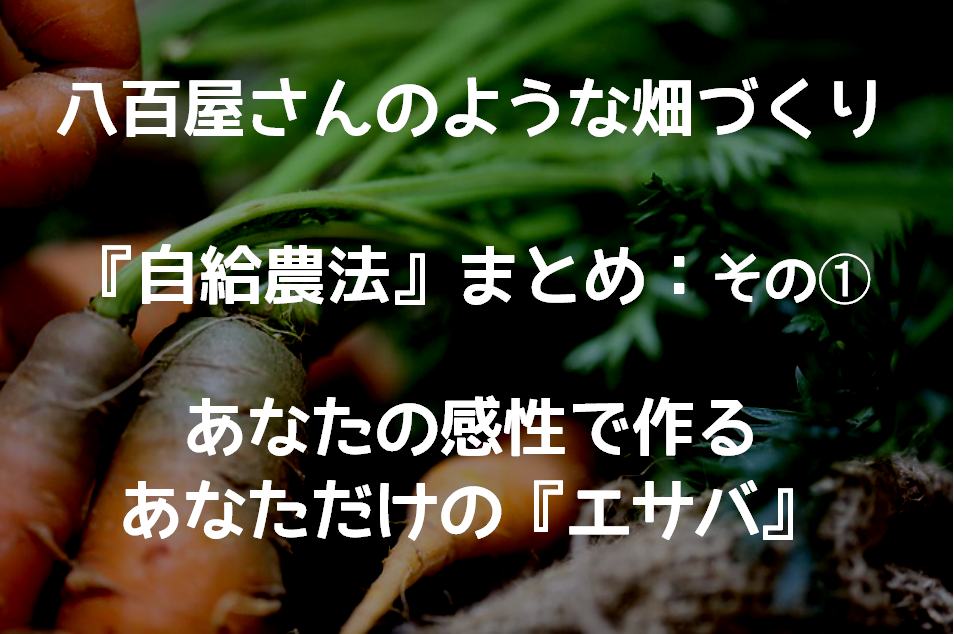
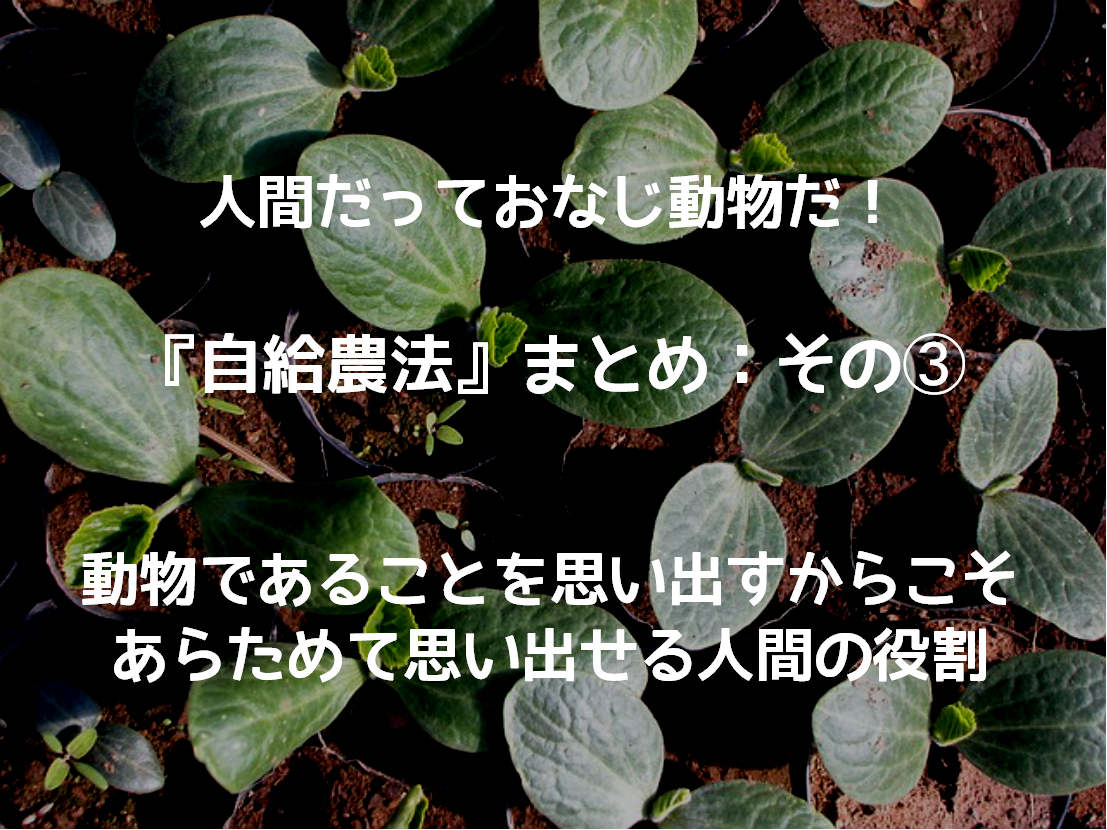
コメント