とある自然農講座で学んだ『自給農法』。
忘れないようにまとめているこのシリーズも通算7回目となりました。
以前の記事を見ていない方は、カテゴリー『自給自足あれこれ』からどうぞ。
実習編3回目の今回は、「種の蒔きかた」のお話です。
種のまき方はその種に聞け!

ポットにタネまきをするジャンさん
「そこにすべてがある」と考える『自給農法』。
種のまき方も、正にその言葉のとおりでした。
参考書やマニュアルに書いてあることとは違い、
感性で種をまくとはどういうことなのか??
「種の形」や「芽が出るまでのヒストリー」を感じる
まずは一般的なタネのまき方を見てみましょう。
|
|
|
実はこの「種の厚さの2~3倍の厚さの土をかける」という方法。
なぜそう言われるようになったのかは不明らしいです。
わたしも自分で調べてみましたが…
明確な理由はどこにも書いてありませんでした。
それでは次に自給農法のタネまきの考え方をみてみます。
自給農法では
・種の形
・自然界で土に落ちて芽を出すまでの流れ
などを考えて、まき方を決めます。
例えば…

【豆類】丸や楕円形で、サヤが弾けて飛び、転がって窪んだところに落ちる
⇒くぼみを作ってまく。鎮圧はそこまで要さない。
 【トマト】実の中に小さな薄い種がたくさん。鳥が食べてフンと一緒に落ちたり、実ごと落ちて密集したまま発芽する
【トマト】実の中に小さな薄い種がたくさん。鳥が食べてフンと一緒に落ちたり、実ごと落ちて密集したまま発芽する
⇒集合させてまき、少し埋める。実ごと埋めてもよい。鎮圧は鳥が踏む程度。
物言わぬ種。
でもその形をよく観察すると…
「こうやってまかれたい!」
と主張しているのが聞こえてきそうですね。
それから『鎮圧』(土をおさえること)と言う言葉が出てきました。
種が「芽を出しても大丈夫」と思わせるためにも、
この『鎮圧』はとても重要とのこと。
自給農法では、
「自然界でその種がどのような過程でまかれるのか」
を考えて『鎮圧』の仕方も変えます。
どういうことかと言うと…
鳥や動物が運ぶような種であれば、
その動物が踏んだ重みを想像しながら『鎮圧』するということ。
イノシシがカボチャを食べ、種が入ったフンをしたあと踏んで去る。
⇒カボチャのタネは、イノシシが踏んだぐらいの重みで鎮圧する
なんだかロマンティック(?)ですね。
いつまくの?『まき時』も種や自然が教えてくれる
種をまくのに適した時期である『まき時』。
自給農法ではこの『まき時』も、
その作物や自然に聞いて判断します。
ここで講師のジャンさん語録をどうぞ
「桜の開花時期は南のほうから桜前線で北上してきますよね。
何かの花が咲いたらこの種をまく。
こういう花ごよみが基準として1番正確です。」
日本で昔から使われてきたという花ごよみ。
ぜひ知りたいと思って少し調べてみたんですが…
[花ごよみ まき時]で検索しても
一般的な『まき時』を書いたものしか出てこない。
しぶとく調べ続けてみると、
『農事歴』という言葉に行き付きました。
たぶんこの『農事歴』が
ジャンさんの言う『花ごよみ』と同じような言葉だと思います。
「サクラの花が咲いたらタネをまく」という言葉を聞いたことがありませんか。ここで言う
タネは,キュウリ,カボチャ,ナス,ユダマメ,インゲンなどが挙げられますが,ソメイヨ
シノを含めたサトザクラの開花は,昔から農作業の,本格的な開始を示す大事な指標として
とらえられてきたのです。~中略~畑は,土地の高低,日光を妨げる木の有無,よく吹く風の向きなど,非常に狭い範囲の気
象条件によっても左右されます。これを微気象と言います。観察を通して,最終的には自分
の畑だけの農事暦を作ることが,有機栽培がうまくいく秘訣と言えるでしょう。
~中略~
花の開花や虫や鳥の出現,天候の変化,行った農作業,病害虫の被害など,気づいた点を
併せて,日記に記録します。
桜は本当に日本人にとって特別な花なんだな~と感心。
そしてこの記事にもあるように、
最終的には「自分だけその土地だけの花ごよみ」
を作るのがベストなんでしょうね。
もっと詳しく知りたい方は、
『二十四節季』とか『雑節』なども調べて参考にするとよさそう。
自給農法では収穫時期=まき時
自然界の力を活かせるよう『感性』を使う自給農法。
感性で『まき時』を考えると下のような答えが出てきます。
自然界で植物が実や種を土に落とす時期=『まき時』=『収穫時期』
植物が子孫を残そうと種を落とす時期が、
自然界にとっての『まき時』。
よくよく考えてみれば当然です。
収穫(間引き)と同時に種まきをする自給農法。
その方法論が理にかなっているのだと改めて気づかされます。
まとめ:感性でまく自給農法の種まき

私も手作りポットに種をまいてみました
・種の形を観察すれば、その種がどうやってまかれたいのか分かる
・その種が土に落ちて芽が出るまでのヒストリーを想像して覆土や鎮圧の仕方を決める
・『まき時』は、自然界の流れを花ごよみや二十四節季などから読み解く
・その植物が子孫を残そうとする時期、人間目線で言えば『収穫期』が自然な『まき時』でもある
感性を使って行動を決定する『自給農法』
自然界がどうやって種をまくのかを考えてみるとおもしろいですね。
わたしの経験を少しお話しすると、
『ササゲ豆(の中でも小さい品種)』は、
サヤを弾けさせて種を飛ばすとき、
よくない種は飛んで行かないのです。
そもそもサヤが弾けなかったり、
弾けたあとくるくると巻いたサヤの中に残っていたりします。
「よくできてるな~」と思って見ていました。
自給農法ではこのように観察を繰り返しながら、
経験と感性で自分だけの『エサバ』を作っていくのです。
それでは今回はここまでです。
次回につづく。







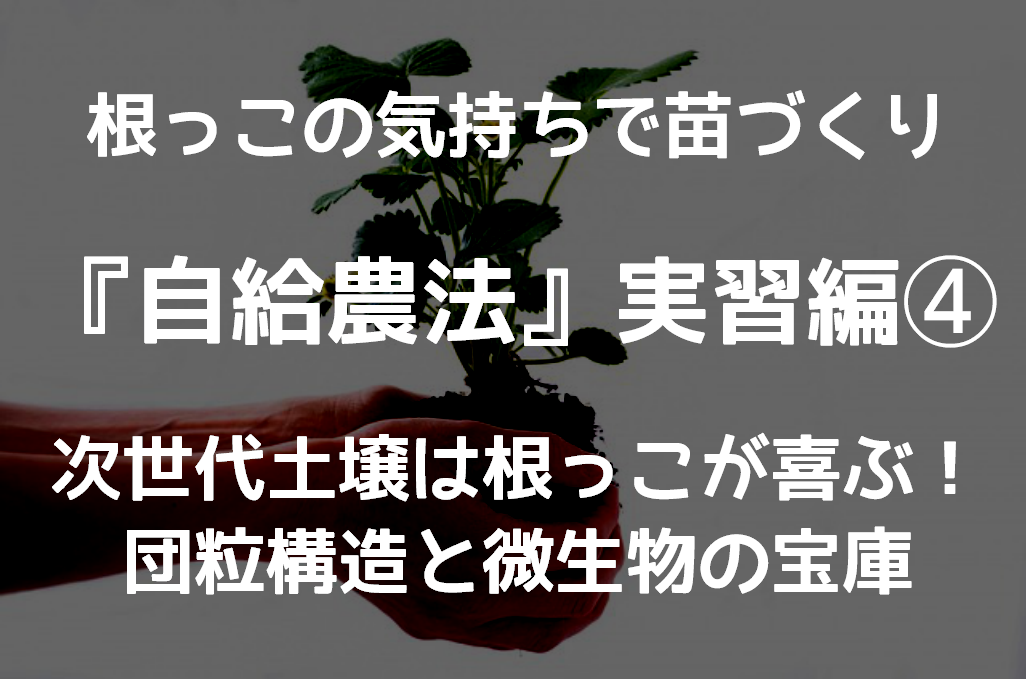
コメント